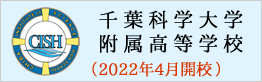教員検索

大高 泰靖 (おおたか ひろやす) / Hiroyasu Ohtaka
私たちが飲んだ薬は、その多くは胃腸で吸収され、血液により全身に届けられ、患部で薬が効きます。薬が血液と共に全身を流れる際に、血液に含まれるタンパク質(血漿タンパク質)と結合し、その結合のし易さが薬の効果に影響を与えます。 そのため、いろいろな薬について、血漿タンパク質との結合し易さを測定すると共に、複数の薬を併用した場合にどのようになるかを調査しています。これらの結果を、薬の効き目に個人差がある現象の解明や各人の健康状態に応じて薬の量を調整するテーラーメード医療に役立てようと考えております。
| 所属 | 薬学部 薬学科 教授
薬学研究科 薬科学専攻 教授 |
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) ( 岡山理科大学 2001年 3月 ) |
| 専門分野 | 分析化学 、生物物理学 |
| 学歴・職歴 | 2001年3月 岡山理科大学 大学院 工学研究 システム科学専攻 博士課程 修了 2001年4月~2005年3月 ジョーンズ・ホプキンス大学(米国) 生物学科 博士研究員(~2004年3月)、助手(~2005年3月) 2005年4月~ 千葉科学大学 薬学部 薬学科 助手・助教・講師・准教授を経て現職 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な担当科目【学部】 | 基礎薬学物理、薬品分析学Ⅰ、薬品分析学Ⅱ、薬品物理化学Ⅰ、薬品物理化学Ⅱ、物理・化学系薬学実習、薬学入門、早期体験学習・銚子学、キャリアプランニング、薬物乱用防止啓発活動、卒業研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な担当科目【大学院】 | (博士課程) 生命科学ゼミナールⅠ、特別講義Ⅰ、特別研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な論文・著書 |
<著書>
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学会 | 日本薬学会、日本熱測定学会、総合危機管理学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 研究室ホームページはこちら ◯ 出張講義テーマ 薬剤師資格と薬学部で学ぶこと エイズ感染の現状と新治療薬の創り方 クエン酸と重曹を利用した実験 ◯ 公開講座、出張講義・実験実績 薬物乱用防止教室 (2013/12-現在) 計290回(銚子・旭・神栖市の小中学校を中心に) 一般向け公開講座 (2011/10-現在) 計11回(千葉、東京にて) 出張講義 (2005/4-現在) 計53回(千葉、茨城、東京、山梨、岡山、静岡などにて) 体験実験講座 (2005/4-現在) 計26回(銚子市、神栖市の小学校・中学校・高校にて) 教員免許状更新講習会 講師 (2013/8-現在) 計6回(千葉科学大学にて) ◯ 教育上の役割 入試広報室参与、学務部次長、教学支援部次長を歴任 ◯ 作成プログラム Androidタブレットと学生証内蔵NFCタグを用いたポータブル出席登録補助システム 薬学共用試験OSCE用 時間管理プログラム(Windows OS) |